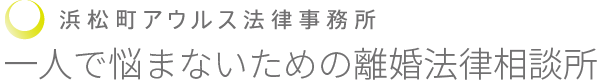婚姻費用・養育費
目次
1. 婚姻費用について
-
婚姻費用とは
夫婦の間では、夫婦や子どもの生活費などの分担について、一方(権利者)は他方(義務者)に請求することができ、これを婚姻費用の分担請求といいます。
婚姻費用の月額は、夫婦の年収・子どもの年齢・人数を基本的な考慮要素として算定されます。
この算定方法は裁判所のホームページで公開されており、実務上「算定表」と呼ばれています。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.htmlただ、実際は、毎年の年収に変動があり年収の認定が難しかったり、妻が居住する不動産の住宅ローンを夫が支払っているなど算定表では考慮されていない個別の事情があったり、なかなか算定表どおりに行かないことも多いです。
婚姻費用は、夫婦が離婚又は別居解消に至るまで支払いが続くことになりますので、婚姻費用については、一度弁護士に相談することをお勧めします。 -
婚姻費用と住宅ローンについて
婚姻費用を取り決めるにあたって、夫婦の一方が、他方が居住する自宅の住宅ローンの支払いをしている場合は、毎月のローンの支払いを、婚姻費用の分担額にどのように反映させるかが問題になります。
東京家裁平成27年月17日審判は、夫が自宅を出て、妻及び子らと別居し、賃貸物件で居住しつつ、妻及び子らが居住する自宅の住宅ローンの支払いをしていた事例です。
この事例では、裁判所は、夫が住居費を二重に支払っていることとなるため、妻の収入(200万)に照らした住居費相当額(2万7940円)を、毎月の婚姻費用の分担金の標準額から控除することとしました。
住宅ローンの考慮方法としては、他に、住宅ローン支払額の何割かを義務者の総収入から控除する方法などがあります。 -
有責配偶者からの婚姻費用の請求
婚姻費用を請求する権利者に、別居や婚姻関係破綻の主たる責任がある場合は、義務者は権利者の生活費相当分については、婚姻費用について責任を減免されます。
例えば、東京高裁平成31年1月31日決定は、妻が、子を監護する夫に対して、婚姻費用の分担を求めたケースです。
このケースで、裁判所は、- 別居の直接の原因は妻の暴力行為にあったこと
- この暴力行為による別居の開始がきっかけとなって、婚姻関係が一挙に悪化したこと
- 暴力行為から別居に至る婚姻関係の悪化の経過の根底には、妻の長男に対する暴力とこれによる長男の心身への深刻な影響が存在すること
などの事実から、別居と婚姻関係の深刻な悪化については、妻の責任によるところが極めて大きいと判断しました。
そして
- 妻は、栄養士及び調理師として稼働し、330万円余りの年収があり、夫が住宅ローンの返済をしている住居に別居後も引き続き居住していること
- 相応の生活水準の生計を賄うに十分な状態にあるということができること
- 夫は、会社を経営し、約900万円の収入があって、それ自体は妻の収入よりかなり多いが、住宅ローンとして月額約24万6000円を支払っており、さらに、別居後に住居を賃借、長男を養育しているが、その住居の賃料及び共益費(月額合計18万6000円)、私立学校に通学する長男の学費(年額91万9700円)や学習塾の費用(月額約4万円)などを負担していること
などの事実から、別居及び婚姻関係の悪化について極めて大きな責任があると認められる妻が、夫に対し、婚姻費用の分担を請求することは、信義に反し、又は権利の濫用として許されないというべきであると判断しました。
婚姻費用の分担請求が認められないケースとして、参考になると思います。
2. 養育費について
-
養育費とは
親権者(監護親)が、親権者とならなかった親(非監護親)に対して請求する子どもに関する費用を「養育費」といいます。
未成年の子どもは、自立するまで、自身の生活に必要な費用をまかなうことはできません。子どもの生活に必要な費用は、夫婦が離婚したといえども、父母で分担するべきです。法律でも、親権者となった親も、親権者とならなかった親も、子どもに対する扶養義務が定められています(民法820条、766条1項、877条1項)。多くの場合、養育費は、「毎月定額を支払う」という条件となります。そして、養育費の月額は、父母の年収・子どもの年齢・人数を基本的な考慮要素として算定されます。
この算定方法は裁判所のホームページで公開されており、実務上「算定表」と呼ばれています。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.htmlこの算定表に基づく金額が、養育費を取り決めるにあたって基本となります。しかし、事案によっては、この算定表だけでは不十分な場合があります。例えば、「子どもが私立学校に通っている」「離婚後も、母子が住む不動産のローンを父が支払っている」等の特別な事情がある場合は、個別の事情を金額に反映させる必要があります。
-
養育費の始期・終期について
-
養育費の始期について
離婚に伴い、養育費の月額を取り決める際、いつから養育費を支払うのかという点(始期)についても取り決めていることが通常です。多くは、離婚した月から、毎月養育費を支払うことで合意しています。
では、養育費を取り決めていなかった場合は、どうでしょうか。
この場合、実務上、養育費は、養育費を請求する内容証明が届いた時や、調停を申し立てた時などの「養育費の支払いを請求した時」から発生することとしています。そして、養育費の月額が合意できた時点で、請求時に遡って未払い養育費を精算することになります。もっとも、子を認知した場合の養育費については、子の出生時からの養育費を認めた審判例があります(大阪高裁平成16年5月19日)。
-
養育費の終期について
成人は、自分で生計を立てることが原則ですので、養育費の終期は、「未成年者が成人に達するまで」が原則です。
もっとも、養育費の終期を、子が大学を卒業するまでとする合意もできますし、実務上よく行われています。
なお仮に、養育費の終期を大学卒業までと合意していなくても、親は子に対して扶養義務(民法877条1項)を負うため、成人に達し、大学生となった子から、非親権者の親に対しては、生活費を請求することもできます。
-
-
養育費における学費の考慮方法について
算定表では、公立中学校・公立高校に関する費用が考慮され、養育費の分担額が計算されています。
それでは、私立学校に進学した場合や、専門学校、大学等に進学した場合、養育費として請求できるのでしょうか。
まず、義務者が進学を承諾していた場合は、進学費用を負担する必要があります。承諾は、黙示でよく、受験を物理的・精神的に援助していた場合などは、承諾があったと認められることが多いです。
また、義務者の収入・学歴・地位などから、私立学校への進学が不合理でない場合には、その費用の一部を負担することになります。
実際、どの程度分担することになるかは、父母の双方の収入、子の就労の有無や、奨学金を受給しているかなどの事情を考慮して決められています。 -
養育費の一括払いについて
養育費は、子供の毎日の生活費のための費用ですので、通常は、養育費は、毎月1度、定額を支払うという内容で合意しています。
それでは、将来の養育費を一括払いすることは可能なのでしょうか。
そもそも、一括払いができるだけの十分な資産があることが前提ですが、父母が合意すれば、養育費を一括払いすることとする合意も有効です。
ただし、その場合、養育費を受け取った親権者が、養育費を浪費してしまい、追加の支払いを求めて紛争になってしまうケースもありますし、また、一括払いの合意をしていなければ、事情が変更したことによる養育費の増減がありうる場合に、一括払いの合意をしていると、事情変更が認められにくくなるケースもあります。
養育費の一括払いをするときは、事前によく利害得失を考えておく必要があります。 -
養育費の増減について
-
養育費増減の可否
離婚に際しては、子どものために養育費を取り決める必要がありますが、いったん養育費を取り決めた後も、父母の収入の増減や再婚など、養育費を取り決めた当時から、事情が変化することがあり、一定の事由がある場合は、養育費の増減を求めることができます。この場合は、従前の養育費額が決められた際の経緯等の関係事情も考慮して、適切な養育費の金額が決定されることとなります。 -
養育費の減額を認めた裁判例(東京高裁令和元年8月19日決定)
■事案の概要
この事例では、離婚の際に、養育費月額15万円(子どもは3名)とし、母と子らが生活する住宅の住宅ローン月額10万円を完済まで支払うこと、父が住宅ローンを支払っている場合は、その支払額を養育費から差し引く旨の条項があったというケースで、父が養育費の減額を求めて調停を申し立て、裁判所の審判に移行しました。■判断の概要
裁判所は、協議離婚時に公正証書で定めた養育費の額(合計月額15万円)が住宅ローンの支払に関する合意と不可分一体のものとなっており、合意の真の意味は、未成年者らの養育監護に使用される実際の養育費としては、住宅ローン月額支払額10万円相当額を除いた、月額合計5万円を抗告人に支払うことを約するものであるとして、同養育費の減額請求につき、住宅ローンに関する合意と切り離して養育費のみを減額することは相当でないと判断しました。
養育費の増減の際に、従前の養育費額が決められた際の経緯等の関係事情がどのように考慮されるか、参考になります。
-
-
再婚が養育費に与える影響ついて
-
養育費が減免される場合
親権者が子どもを連れて再婚したとしても、子どもと再婚相手との間で親子関係が当然に発生するわけではありません。そのため、子どもの親権者が再婚をしても、親権者とならなかった実親について、養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。
親権者の再婚相手と子どもが養子縁組をした場合には、再婚相手と子どもの間に法律上の親子関係が発生します。養子縁組をしても、実親が親でなくなるわけではありませんので、扶養義務が消滅するわけではありませんが、養親の扶養義務は実親の扶養義務に優先し、実親は養育費の支払いを減免されると考えられています。
ただし、再婚相手の養親が無資力である場合や、実親の収入に余裕がある場合は、実親が扶養義務を負うこともあります。 何をもって「十分に扶養義務を履行できない」といえるかどうかは、いろいろな考え方がありますが、ケース・バイ・ケースとなります。福岡高裁平成29年9月20日決定でも、「何をもって十分に扶養義務を履行することができないとするかは、生活保護法による保護の基準が一つの目安となるが、それだけでなく、子の需要、非親権者の意思等諸般の事情を総合的に勘案すべきである。」と判断されています。 -
特殊なケース
実親が、養子縁組の事実を知りながら、養育費の支払いを続けるケースもあります。この場合の婚姻費用については、どのように計算するのでしょうか。
大阪高裁平30年10月11日決定は、妻が再婚し、連れ子と再婚相手は養子縁組をしましたが、別居し、再婚相手に婚姻費用の分担を求めた事例です。連れ子の実の父親は養育費の支払いを続けていました。
裁判所は、この事件で、いわゆる標準的算定方式を参考に婚姻費用分担金の額を試算した上で、子の実父から支払われた養育費については、この試算額にもとづく未払婚姻費用分担金から、養育費の既払い分を控除しました。
-